田起こしや土づくりを終えて、季節は冬へ。
春からはいよいよ、ぼくにとって初めての米作りの一年が始まります。
この冬は、田んぼを休ませながら、自分自身も心と体を整える大切な時間。
今回は、そんな「初めての米作りを迎える冬」にどんな準備や心構えをしているのか、
そして冬の田んぼの過ごし方について紹介します。
◆ 冬の田んぼは“休む時間”
稲を育てる準備を進めてきた田んぼも、今はすっかり冬模様。
霜が降り、地面は冷たく締まり、空気も透き通っています。
地域の農家さんに教わったのは、
**「田んぼも人と同じで、冬は休ませてやる時期なんや」**という言葉。
この時期に土を落ち着かせておくことで、春には柔らかく、栄養を含んだ良い土になるそうです。
作業の手を少し止めて、自然の力に任せる。
それもまた、農業の大事な一部なんだと感じます。
◆ 見回りと“冬の静けさ”
作業は少なくても、冬の間も田んぼをときどき見回ることが大切です。
風で飛ばされたわらが水路をふさいでいないか、イノシシが入っていないか。
ある朝、霜の降りた田んぼを歩くと、自分の足跡がくっきりと残っていました。
その跡を眺めながら、
**「来年の春、この場所で本当に稲を育てるんだな」**と、じんわり実感がわいてきました。
何もしていないようで、確実に時間が流れている。
静かな冬の田んぼには、春への息づかいが感じられます。
◆ 機械のメンテナンスと倉庫の整理
冬のうちに欠かせないのが、農機具のメンテナンスです。
初めて使ったトラクターも、泥を落とし、オイルを替え、ボルトのゆるみを点検。
おじさんに言われた言葉が印象的でした。
「機械は、使わん時こそ手をかけるんや」
確かに、春にトラブルが起きると大変。今のうちに手を入れておくことで、安心して田植えを迎えられます。
倉庫も片づけながら、必要な道具を見直す時間にしています。
軍手や長靴、肥料まきのバケツなど、小さな準備が来年の助けになる気がします。
◆ 冬は“学びの時間”
外の作業が少ない分、冬は知識を深める季節でもあります。
本を読んだり、先輩農家さんに話を聞いたり、YouTubeで稲作の動画を見たり。
今年学んだことをノートにまとめながら、
「来年はこんな肥料を試してみよう」
**「雑草対策はもっと早めにやろう」**と、イメージを膨らませています。
農業は、計画と実践の繰り返し。
今のうちに頭の中で“春のシミュレーション”をしておくことで、きっと慌てずに動けるはずです。
◆ 地域とのつながりを育てる冬
冬になると、地域では用水路の掃除や共同作業があります。
寒い朝に焚き火を囲みながら、おじさんたちの昔話や経験談を聞く時間はとても貴重。
「冬のうちに顔を覚えてもらえたら、春に助けてもらえるぞ」
と笑って言われた言葉に、地域との関わりの大切さを実感しました。
農業はひとりで完結しない仕事。
人とのつながりが、春の田植えを支えてくれるのだと思います。
◆ 冬の風景と心の準備
冬の田んぼは、静かでどこか凛とした美しさがあります。
朝日に照らされて霜が光る瞬間、冷たい空気を吸い込むと背筋がしゃんとします。
作業の合間に焚き火をしながら温かい缶コーヒーを飲む。
そんな小さな時間が、**次の季節に向けての“心の栄養”**になっています。
「何もしていないようで、確かに農の時間が流れている。」
冬の田んぼには、そんな穏やかなリズムがあるのだと思います。
◆ 春への決意
来年は、ついに自分の手で田植えをする初めての年。
不安もありますが、それ以上に楽しみが大きいです。
土の匂い、苗の成長、水の音——。
そのすべてを自分の手で感じながら、少しずつ農家としての一歩を踏み出していきたいと思います。
冬はそのための“助走期間”。
焦らず、でも確実に。
静かな田んぼの中で、春への準備を進めています。
◆ 次回予告
次回は「農業初心者の一年計画づくり」について。
春からの初めての米作りに向けて、どんな流れで作業が進むのかを整理していきます。
田起こし・代かき・田植え・草刈り・収穫まで、一年のスケジュールを立てることは農業の第一歩。
地域の方のアドバイスも交えながら、無理のない計画の立て方を紹介します。
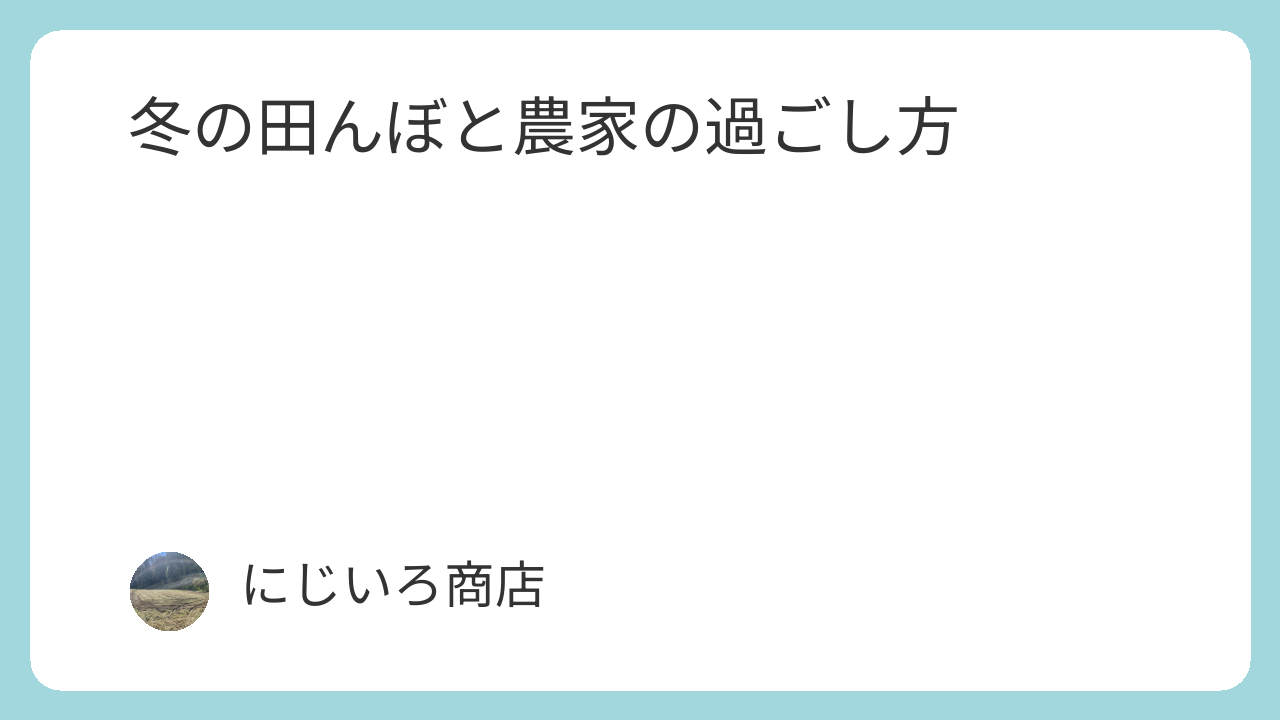
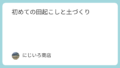
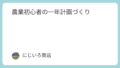
コメント