米づくりを始めようと思っても、最初に悩むのが「何をそろえればいいのか」というところではないでしょうか。
私も最初はまったくの素人で、田んぼに立つのも久しぶり。道具の名前も使い方も分からず、地域の方々に教えてもらいながら少しずつ覚えていきました。
今回は、そんな私の経験から「これがあると本当に助かる!」と思った米農家の必需品を紹介します。
実際に使ってみて感じたことを交えながら、初心者の方にもわかりやすくまとめました。
1. 軽トラ:農家の足と運搬の頼れる味方
まず紹介したいのは、農家にとって欠かせない「軽トラック(軽トラ)」です。
田んぼと家の行き来はもちろん、苗や肥料、収穫した米、さらには草刈り機などの道具を運ぶのにも大活躍します。

私の場合、最初は「普通車でなんとかなるだろう」と思っていましたが、すぐに考えが変わりました。
田んぼのあぜ道は狭くぬかるみやすいので、車高の低い普通車ではすぐスタックしてしまいます。軽トラなら小回りが利き、悪路にも強い。荷台も広く、どんな荷物も積み込みやすいのが魅力です。
地域の方から「軽トラは農家の足だよ」と言われた意味が、今ではよく分かります。
通勤車というより、まさに“働く相棒”です。
ポイント:
- 4WDタイプだと、ぬかるみでも安心。
- 荷台カバーをつけると雨の日も便利。
- 中古市場も豊富で、10万円台から探せることもあります。
2. 長靴・作業着・軍手:快適さと安全を守る三種の神器
田んぼ作業で一番大事なのは「動きやすさと安全」です。
泥に足を取られたり、水が冷たかったりすると、思った以上に体力を奪われます。
私が愛用しているのは、膝上まである防水長靴と、速乾性のある作業着。
夏場は通気性のいい素材を選び、首にはタオル、頭には広めの帽子。これだけで作業の快適さが全然違います。
そして忘れてはいけないのが軍手や手袋です。
トラクター作業や草刈り、苗の運搬など、どんな場面でも手の保護は欠かせません。
私は、細かい作業には「薄手のゴム手袋」、重い作業には「厚手の滑り止め付き軍手」と、用途によって使い分けています。
最初は「なんでもいいや」と思っていましたが、手袋ひとつで作業の疲れ方がまるで違うことに驚きました。
おすすめポイント:
- 脱ぎ履きしやすい長靴は、田植えや草刈りの日に◎
- 洗ってすぐ乾く作業着は毎日の味方。
- 手袋は滑り止め付き・通気性タイプを季節で使い分け。
- UVカットの帽子やネックカバーもあると安心です。
3. 草刈り機(刈払機):田んぼの美しさを保つ影の主役
田んぼの周りの草を放っておくと、虫が増えたり、見た目も悪くなったりします。
「農業は草との戦い」と言われるほど、草刈りは大切な作業です。
主に田んぼ周りの「あぜ」の草刈りを定期的に行います。
草刈りが終わったあと、田んぼがすっきりと見渡せると、不思議と気持ちまで明るくなります。

ポイント:
- エンジン式はパワーが強く、広い面積におすすめ。
- 電動式は軽くて静か、小規模な田んぼ向き。
- 草刈り後にすぐトラクターで耕すと草が絡みにくいです。
4. トラクター:田んぼの相棒

米づくりの心臓ともいえる存在が「トラクター」です。
田起こしや代かきなど、田んぼの土を整える作業を一手に担ってくれます。
私の場合、地域のおじさんが「倉庫にトラクターを置かせてくれ」と言ってくれたのがきっかけで、自由に使わせてもらうようになりました。おかげで高価な機械を買わずに、実践しながら学ぶことができました。
最初のうちは草が絡まったり、耕す深さを間違えたりと失敗ばかりでした。
でもおじさんが「草刈りのあと、草が短いうちにすきなさい。足跡が消える前が一番いい」と教えてくれてからは、作業がぐんとスムーズになりました。
この“タイミングの感覚”は、教科書には載っていない地域の知恵そのものです。
ポイント:
- 中古でも性能の良いトラクターは多く、共同利用もおすすめ。
- 作業後の泥落としとオイル点検を習慣に。
- ロータリー部分の草巻きつきは早めにチェック。
5. とりあえずは買わずにリースした方が良いもの
農業を始めたばかりの頃は、何もかも揃えたくなります。
しかし実際に使ってみると、「思ったより使う頻度が少ない」「自分の田んぼの広さには合わなかった」など、失敗も出てきます。
そこでおすすめなのが、リースやレンタルで試してみることです。
例えば、田植え機やコンバイン(収穫機)は高額で、保管場所やメンテナンスも必要です。
小規模な田んぼなのであれば田植え機やコンバインは年に1~2日程度しか使いませんし、必要な時期だけ借りられて、使い終わったら返すだけなので本当に楽です。
また、地域によっては農機具の共同利用制度や、JA・市町村が運営するレンタルサービスもあります。
「買うのは来年でもいい」と思えるくらい、今はリース環境が整っています。
最初の数年は、使い心地を確かめながら、自分に合う機械を見つける期間と考えるのが良いと思います。
ポイント:
- 田植え機・コンバイン・乾燥機などはリースが現実的。
- 地域の農協(JA)や自治体に相談すれば手配可能。
- 購入するなら、1年通して使う道具から少しずつ。
🌱 おわりに:道具を通して広がる、米づくりの世界
最初は「こんなに道具が必要なのか」と不安でしたが、使いこなせるようになると、それぞれが頼もしい“仲間”のように思えてきます。
地域の方の知恵や助けを借りながら、自分なりのペースで田んぼを整えていく——。
その積み重ねが、少しずつ自信につながっていくのだと思います。
これから米づくりを始めようという方は、まずは道具選びから。
そして、分からないことは地域の先輩農家さんに聞いてみてください。
きっと、道具以上に大切な“経験の種”を分けてくれるはずです。
🌾 次回予告:「初めての田起こしと土づくり」
次回は、実際にトラクターを使って行う初めての田起こしについてお話しします。
草の処理やタイミング、土の状態の見極め方など、地域の方に教わった“土と向き合う最初のステップ”を紹介する予定です。
いよいよ、田んぼづくりの実践編に入ります。
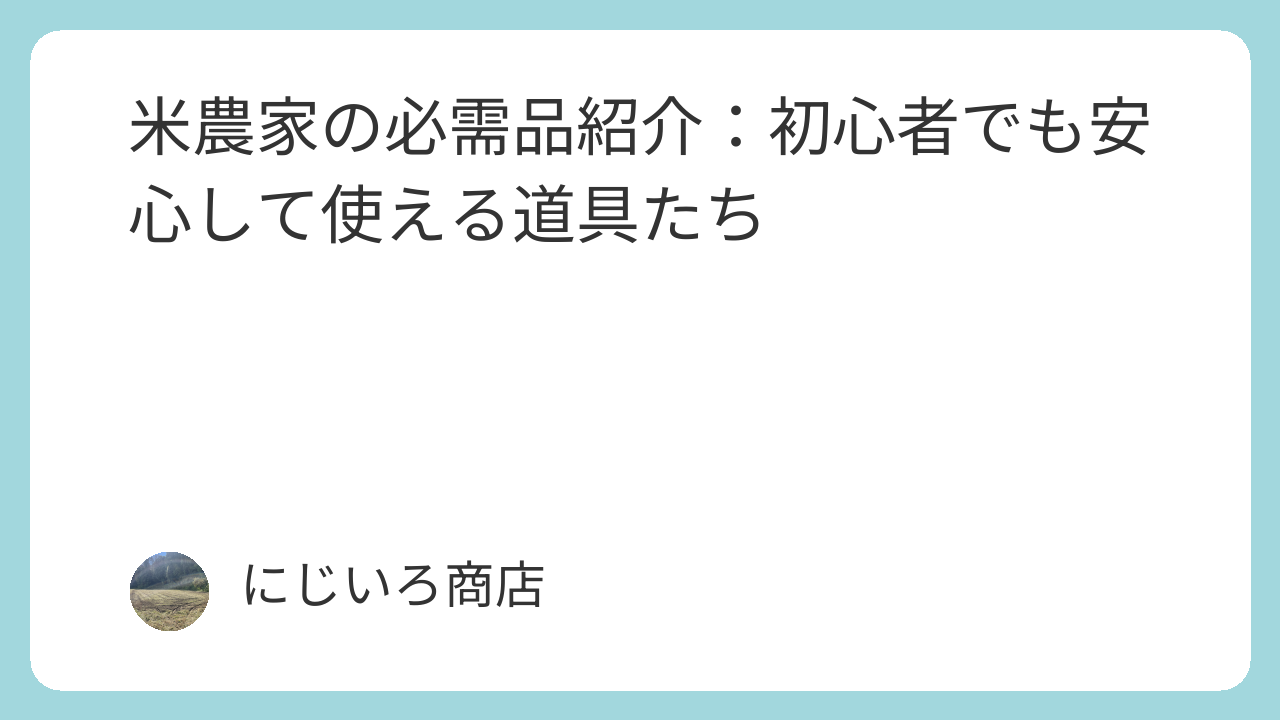
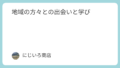
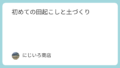
コメント